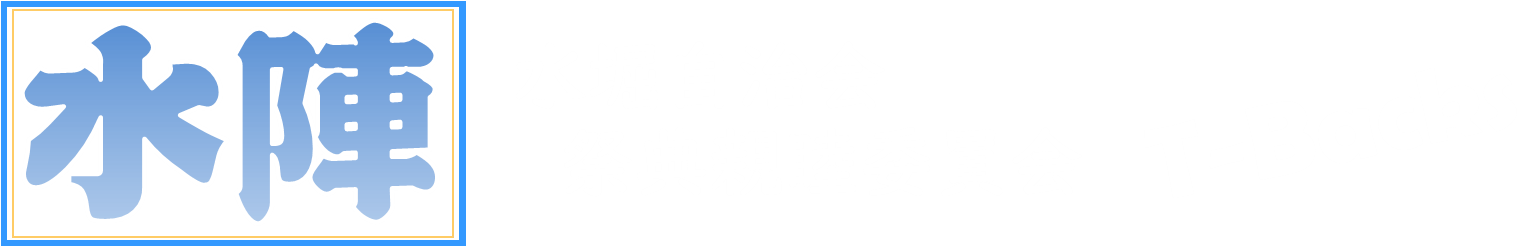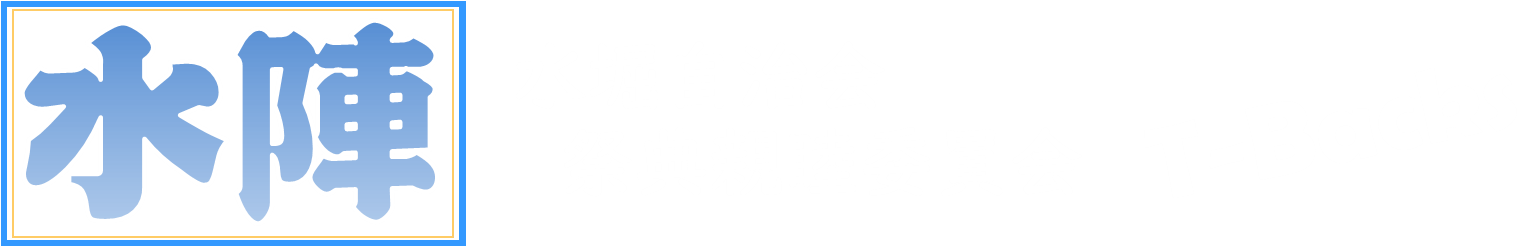
もっと知りたい方へ
用語解説と注意事項
あ行
- 淡海国玉神社
-
旧見付学校の北側にある神社で大国主命ほか17柱の神々をお祀りしています。
遠江の神々をあわせた神社のため、別名を「総社」ともいい、さらに見付の中心部に位置していることから「中の宮」ともいいます。
裸祭では大祭1日目の夜中に矢奈比賣神社からこの神社に向けて神輿が渡ります。
公式サイト
- 鬼踊り
-
矢奈比賣神社の拝殿に入り(堂入り)、床板を踏み鳴らしながら鈴の音に合わせて「ヨイショ」の掛け声で行われる練りのこと。
最初は西区の梯団のみですが、西中区、東中区、東区の順に堂入りが進むと拝殿内の集団が大きくなり、祭りもクライマックスに向けて盛り上がっていきます。
0時過ぎに元門社が榊を手に堂入り(〆切)すると祭りは最高潮に達します。
また〆切の堂入りをきっかけとして幣殿内で渡御に向けた神事が斎行されます。
令和5年(2023年)度の様子はこちらより。
- おもてなし水陣
-
水堀独自の取り組み。町内外を問わず、会所へ来ていただいた方を主に飲食でもてなします。
例年であれば生ビール、焼き鳥、おでん、かき氷といった軽食を準備しています。
令和5年(2023年)度の様子はこちらから。
- お礼参り
-
浜垢離から戻ってきたことを報告するため矢奈比賣神社へお参りします。
道中は屋台を引き回してお囃子演奏をします。
令和5年(2023年)度の様子はこちらから。
か行
- 会所
-
大祭期間の間に各祭組の中心となる場所です。
祭壇を設け、矢奈比売神社より拝領した榊を中心に、半返しを受けたお神酒、塩、米等の供物を備えます。
水陣では水堀会館前に会所を設営し、大祭当日の10時に会所開きを行います。
令和5年(2023年)度の様子はこちらから。
- 門提灯
-
見付本通り(栄光への道)と不用小路の交差点に掲げる1対の提灯のことです。
水陣の練りの集団はここから見付本通りへ出入りします。
- 還御
-
大祭2日目の17時に淡海国玉神社(総社)から矢奈比賣神社に向けて神輿が出発します。途中、西坂、河原でお神酒献上を受けた後、境松御旅所、三本松御旅所を経て矢奈比賣神社へ到着します(着御)。
拝殿前では何十回と神輿を振り上げ(霊振り)た後、拝殿に納めます。この後、着御奉告祭の祝詞奏上が行われ、8日間の裸祭りが終了します。
- 警固
-
裸の集団を管理・統率する役割の人達。白丁と呼ばれる白い装束を上半身にまとっています。
水陣の場合は、警固長が警固を選出します。例年10名程度です。
大祭参加者は必ず警固の指示に従い行動してください。指示に従えない方は参加できません。(追い出されます)
また、道中・境内で困りごとが発生した場合は、警固に助けを求めてください。
- 警固研修会
-
警固長より裸の集団を統率していく役職者(警固)を任命して白丁を配布します。
また、主に警固向けではありますが、祭典親睦委員全員と大祭当日の流れと役割の認識合わせを行います。
- 警固長
-
警固を統率するための長で、各祭組で1名ずつ選出し、その年の祭組の顔となります。(パンフレットに顔写真も載るので名実ともに顔になります。)
裸祭保存会にも所属し、裸祭の全体の運営方針、決定事項を各町内に展開する役割も担います。
- 刻限触れ
-
西区梯団のほかの祭組の会所を互いに訪問し、あいさつを交わす儀礼です。
水陣からは警固1~2名が裸数名を率いて各町内を訪問します。逆に、各町内からも同様の規模で水堀会館前の会所に来るので、総代と警固長を中心に迎えます。
- 輿番
-
渡御で神輿を担ぎ、還御では神輿を載せた車を曳く役職です。権現と地脇(東中区)が1年交代で担当しています。
渡御・還御の際に輿番以外が神輿に触れるのは不敬にあたります。お渡りの際は神輿が速やかにお堂から出られるよう、輿番の指示に従ってください。
- 腰蓑
-
大祭当日に着用します。大人連参加者は必須、子供連参加者も着用が望ましいです。
見付地区の商店で購入してもよいですが、自治会で手配した稲藁を使って自分で作ることもできます。
さ行
- 祭事始
-
裸祭りの開始を報告する神事で、元宮天神社旧社地にて斎行されます。
水陣からは自治会長(総代)、保存会青年部が参加します。
- 先供
-
正式名称を「神輿御先供係」といいます。
神職とともに裸祭の期間中のほぼすべての神事に参加し、渡御・還御の際はお道具(御幣、弓、矢、太刀、大鉾、金幣など)を持ち神輿の前でお供をします。
世襲が原則で、親から子、孫へと代々役割を引き継いでいます。
- 参加条件
-
以下条件をすべて満たす方が参加できます。
①各祭組の会所から参加する人。(道中など途中からの参加はできません)
②裸祭りを愛し、しきたりを守る人。(ルールを守れない方はダメ)
③役員(警固)の指示に従う人。
④浜の水で心身の潔斎をした人。(浜垢離で清めていない方はダメ)
⑤身なりの正しい人。
※入れ墨をした人、暴力をふるう人は参加できません!!
- 鈴
-
シャンシャンと鳴る鈴の音に合わせて「ヨイショヨイショ」の掛け声を出します。
鈴を振ることができるのは「一番觸」「二番觸」「権現」の3祭組のみです。決して触れないようにしてください。
- 全体会議(町内)
-
裸祭期間中で各役員・部局(子供会・中学PTA・組長・副組長)にお願いする事項とタイムスケジュールについて打合せ・認識合わせをします。
また、会議終了後、参加された組長へ軒花・手拭い等を渡し、購入された世帯へ配布してもらいます。
- 総代
-
各祭組の総責任者です。
水堀の場合、基本的には自治会長が総代を務めます。
た行
- 町内回り
-
鐘をもって祭りが始まることを町内に触れ回ります。またその道中で初子(その年に生まれた子)がいるお宅を訪問し、お祝いします。
水陣では警固1~2名に加えて裸数名で町内を回ります。(初子の世帯数によっては複数部隊に分かれて回ることもあります)
令和5年(2023年)度の様子はこちらから。
- 梯団
-
裸祭は見付地区を4つに大別し、大祭当日はその集団を単位として行動(道中練り・堂入り)します。
梯団名は「西区」「西中区」「東中区」「東区」の4つで、水陣は「西区」に所属しています。
各梯団の構成は以下の通りです。
西区 :中央町(月松社/境松)、
加茂川通(元喬車)、
河原町(龍陣)、
梅屋町(梅社)、
西坂町(根元車)、
水堀(水陣)、
一番町(一番觸)、
幸町(玄社)
西中区:馬場町(舞車)、
元倉町(元藏社)、
天王町(天王)、
二番町(二番觸)
東中区:宿町(御瀧車)、
新通町(龍宮社)、
清水町(清水)、
中川町(川龍社)、
地脇町(地脇)、
元宮町(元宮社)、
緑ヶ丘(緑ヶ丘)、
北見町(北見)、
美登里町(美登里)、
今之浦5丁目(龍王社)、
今之浦4丁目(大乃浦)
東区 :東坂町(眞車)、
富士見町(元門車)、
権現町(権現)、
住吉町(宮本)、
元天神町(元天神)
- 梯団長
-
各梯団の責任者です。その梯団の動きを取りまとめて統率します。
西区の場合は8町内が持ち回りで担当します。
- 道中練り
-
全28町内が4つの梯団を形成し見付の町内を練り歩きます。以下、水陣・西区梯団の動きです。
①21:00~ 玄社、一番觸に続き、水陣が不用小路から見付本通り(栄光への道)へ出て、西光寺に向かいます。
②21:20頃 西光寺前で西区の各祭組が集合して梯団となり、東へ向かいます。
③21:45頃 西区が淡海国玉神社拝殿を一周し、東へ進みます。(この最中に西中区は総社前を西へ通過します。)
④21:52頃 中央幹線交差点で東中区と擦れ合い(すれ違い))します。
⑤22:05頃 農協前付近で東区と擦れ合います。
⑥22:30頃 三本松御旅所を折り返します。
⑦22:50頃 境松を先頭に祭組単位で堂入りして鬼踊りが始まります。
- 灯籠
-
水堀独自の取り組みとして、水堀公園~水堀会館の道沿いに灯籠を設置しています。
子供会ととんぼの会にご協力いただき祭りを盛り上げる絵を描いてもらっています。
- 渡御
-
「おわたり」とも言います。0:30頃に山神社での神事にて「二番觸」の祝詞が奏上されると、花火が打ち上げられすべての灯りが消された後、乱舞する裸を押し分けて輿番が神輿を担いで社殿の外に出ます。
そのまま暗闇の中、淡海国玉神社(総社)へ向かいます。
渡御の最中は一切の灯りをつけることは禁止されています。カメラのフラッシュはもちろん、たばこの灯り、スマートフォンのバックライトも確実に消灯してください。
淡海国玉神社へ神輿が到着(着御)すると再び花火が上がり、街の明かりが再び灯ります。
は行
- 白丁
-
総代、警固長、警固等の役職者が上半身に身に着ける衣装です。
役付者のみが着用を認められています。水陣の場合は、町内で用意したものをその年の警固長が役付者へ貸与します。
- 浜あそび
-
浜垢離で心身の潔斎をした後、祭組単位で会食をしたり子供や女性だけの練りも行うなど、楽しい時間を過ごしながら大祭に向けて気持ちを盛り上げていきます。
- 浜垢離
-
裸祭参加者の心身を潔斎する神事で大祭の3日前に行います。
松原の神事、海原の神事(海浜修祓)の潔斎が済んだのち、神職、先供、輿番に続いて各町内の氏子全員が海に入り、心身を清めます。
その町内を示すシンボルとして浜印を掲げ、一緒に清めます。
また、大祭当日の会所開きで使うため、小石(なるべく平たいもの)と、浜砂、海水を持ち帰ります。
清めが終わった後は、町内毎にまとまって浜遊び(会食)をします。
※平日(水曜日)ですが、見付地区の小中学校(磐田北小、富士見小、城山中)は1日休校になるので、子供たちへ参加呼びかけをお願いします。
令和5年(2023年)度の様子はこちらから。
- 觸番
-
一番觸、二番觸、三番觸の順に神輿が渡御することを神輿の通り道に知らせます。
一番觸は一番町、二番觸は二番町、三番觸は権現が担当しています。
- 勉強会
-
裸祭りについての知見がない・浅い方に向けて、裸祭りの習わし、しきたり(ルール)や祭典期間中に行われる行事を説明します。
ま行
- 御池の清祓い
-
社殿・境内および氏子全般を潔斎する神事で、大祭前日に行います。
浜垢離の日に海から持ち帰った海水と浜砂で社殿・境内を清めます。潔斎に使った榊は中川に流します。
- 神輿
-
矢奈比賣命の御霊をお運びする輿です。
大祭期間中の8日間は矢奈比賣神社もしくは淡海国玉神社の社殿内に置かれており、大祭当日の21時に御霊が神輿へ移る神事が行われ、0時半頃に渡御します。
大祭2日目の20時に矢奈比売神社へ戻り(還御)、御霊戻しの神事が行われます。
特に渡御・還御の時に神輿を上から見下ろすことがないようにしてください。(神様を上から見下ろすことになり大変な不敬にあたります。)
- 御斯葉おろし
(おみしばさま)
-
見付地区の潔斎のための神事です。大祭期間中に神輿が通る13か所に15本の榊を立て道中を清めます。
榊を立てる場所は(1)社務所、(2)大鳥居、(3)出口井戸、(4)愛宕下、(5)元門、(6)三本松御旅所、(7)東坂梅の木、(8)総社前、(9)西坂梅の木、(10)河原入口、(11)横町土橋、(12)境松御旅所、(13)旧虎屋前です。(2)大鳥居と(5)元門は2本、それ以外は各1本ずつ立てます。
誰でも参加できますが、上下白の衣装(白シャツ・白短パン等)で、神職・先供に続いて駆け足で移動してください。(徒競走ではないので追い越さないこと!)
22時過ぎに花火が鳴りますので、35分間各戸で消灯をお願いします。
令和5年(2023年)度の様子はこちらから。
- 見付天神
- 矢奈比売神社を参照。
- 身なり(正装)
-
裸祭りは正しい身なりを整えた方しか参加できません。
①町印の手拭いの「はちまき」(ねじったりするのはダメ。「水陣」が見えるようにして頭に巻く。)
②さらしの「はらまき」と「ふんどし」(白短パンはダメ。)
③「こしみの」
④「黒たび」(白たびは神職、先供、輿番のみ。地下足袋もダメ。)
⑤「わらじ」
や行
- 矢奈比賣神社
-
この祭の中心となる神社で、見付の東部の丘陵地の上にあり矢奈比賣命をお祀りしている。
また学問の神様ともいわれている菅原道真もお祀りしていることから別名「見付天神」ともいう。
(※)「矢奈比賣天神社」は誤り。
- 山神社
- 矢奈比賣神社境内にある神社。お渡りの前にここで祝詞奏上を行う。
わ行
- 草鞋
-
大祭当日に着用します。大人連参加者は必須、子供連は大人連同様着用が望ましいです。
腰蓑よりも自作の難易度が高いため、見付地区内の商店やインターネットで購入される方が多いです。
サンダルと違い、つま先を草鞋の先へ飛び出してかかとを余らせないのがベストサイズです。大きいサイズは踏まれて脱げやすくなります。
↑