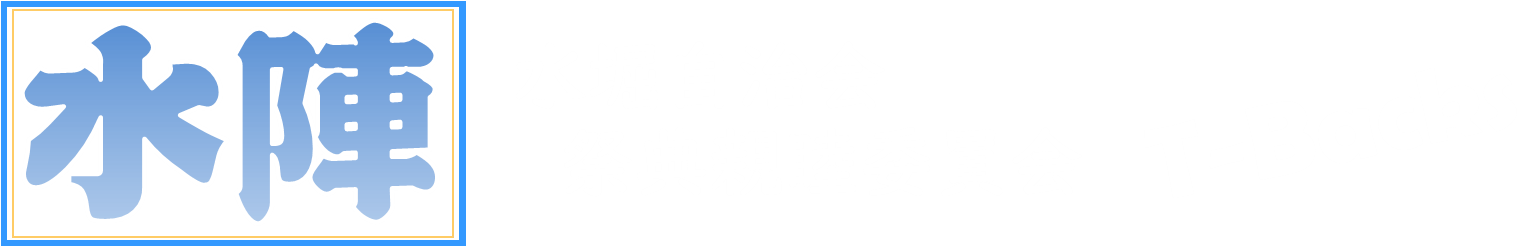令和7年度(2025年度) 見付天神裸祭
日程
今年度の日程は以下の通りです。
- 9月21日(日)
- 祭事始(元天神社)
- 御斯葉おろし(矢奈比賣神社~三本松~境松)
- 9月24日(水)
- 浜垢離(福田海岸)・お礼参り(矢奈比賣神社)
- 9月26日(金)
- 御池の清祓い(矢奈比賣神社)
- 9月27日(土)
- 大祭(矢奈比賣神社)
- 渡御(矢奈比賣神社~淡海国玉神社(総社))
- 9月28日(日)
- 還御(淡海国玉神社(総社)~境松~三本松~矢奈比賣神社)
大祭当日の水陣行程図 NEW
詳細スケジュール
| 日付 | 時間 | 場所(集合場所等) | 役割・会議・イベント | 参加者・出席者 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自治会長 | 自治会 役員 |
警固長 | 保存会 青年部 |
T-Backs | 子供会 | 中学 PTA |
組長 | 副組長 | 他 | |||||
| 8月9日 | (土) | 19:00~ | 矢奈比賣神社 | 保存会 全体会議 | ● | ● | ● | |||||||
| 8月30日 | (土) | 19:00~ | 幸町会館 | 西区梯団会議 | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 8月31日 | (土) | 13:00~ | 水堀会館 | 子供会との打合せ | ○ (委員長) (屋台長) (3B長) |
○ | ||||||||
| 9月6日 | (土) | 19:00~20:00 | 矢奈比売神社 | 保存会 警固研修会 | ● | ● | ○ (委員長) |
|||||||
| 9月13日 | (土) | 13:00~ | 水堀会館 | 灯籠絵入れ、名入れ | ○ | ○ | とんぼの会 | |||||||
| 18:30~19:30 | 水堀会館 | 水陣 裸祭勉強会 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ (役員) |
|||
| 19:30~20:30 | 水堀会館 | 水陣 裸祭全体会議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ (役員) |
|||
| 9月20日 | (土) | 19:00~20:00 | 水堀会館 | 水陣 警固研修会 | ● | ○ (祭典親睦) |
● | ● | ||||||
| 9月21日 | (日) | 9:00~ | 福田海岸 | 海岸清掃 | ○ | |||||||||
| 13:00~ | 水堀会館 | 腰蓑講習会 | ○ | 作りたい人 | ||||||||||
| 21:20~ | 水堀会館 | 御斯葉おろし | 自由参加 | |||||||||||
| 9月22日 | (月) | 19:00~20:30 | 水堀会館 | お囃子練習 | ○ | ○ | ||||||||
| 9月24日 | (水) | 9:00~ | 水堀会館 | 浜垢離 備品準備 | ● | ● | ○ | |||||||
| 9:30~ | 水堀東公園 | 浜垢離 参加者集合 (10:00出発) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 12:00 | 福田海岸 | 海水、砂、石 持ち帰り | ○ | |||||||||||
| 17:00~ | 水堀会館 | お礼参り | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 9月26日 | (金) | 20:00~ | 矢奈比賣神社 | 御池の清祓い | 自由参加 | |||||||||
| 9月27日 | (土) | 0:00~ | 水堀会館 | 御神酒献上・榊受け取り | ● | ● | ○ | |||||||
| 8:30~10:00 | 水堀会館 | 会所設営 | ● | ○ (副会長) (祭典親睦) |
● | |||||||||
| 8:30~24:00 | 水堀会館 | 寄付受付 | ○ (8:30~10:00) (20:00~24:00) |
○ (10:00~20:00) |
||||||||||
| 10:00~ | 矢奈比賣神社 | 大祭 参列 | ● | |||||||||||
| 10:00~ | 水堀会館 | 会所開き | ○ (副会長) (祭典親睦) |
● | ||||||||||
| 10:00~ | 水堀会館 | おもてなし水陣 スタンプラリー受付 |
● | T-Backs女子 | ||||||||||
| 午前~ | 水堀会館 | 料理等準備 | ● | |||||||||||
| 13:30~ | 西区各町会所 挨拶回り | ● | ● | |||||||||||
| 16:00 | 水堀会館 | 祭典参加者 集合 | ● | ○ | ||||||||||
| 17:30~ | 水堀会館 | 子供連 | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 19:00~19:50 | 水堀会館 | 刻限触れ 刻限触れ出迎え |
● | ● | ○ | |||||||||
| 19:00~ | 水堀会館 | 町内回り 初子お祝い |
○ | 初子世帯 | ||||||||||
| 20:30~翌1:00 | 水堀会館 | 大人連 | ● | ● | ● | ● | ○ (給水支援) |
T-Backs女子 (給水支援) |
||||||
| 9月28日 | (日) | 0:30~ | 不用小路 | 門提灯 消灯確認 | ○ | |||||||||
| 1:00~ | 矢奈比賣神社 | 渡御後清掃奉仕 | ○ | |||||||||||
| 10:00~ | 水堀会館 | 会所片付け | ● | ○ (祭典親睦) |
● | |||||||||
| 12:00~ | 水堀会館 | 屋台引き回し | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 18:00~ | 加茂川通り | 還御見送り | ○ (祭典親睦) |
● | ● | |||||||||
| 9月29日 | (月) | 7:00~ | 水堀会館 ごみ集積場 |
軒花 竹回収 | ○ | |||||||||
| 10月4日 | (土) | 19:00~ | 水堀会館 | 裸祭り反省会 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ (役員) |
|
| 10月11日 | (土) | 19:00~ | 幸町会館 | 西区梯団反省会 | ● | ● | ● | ○ | ||||||
- 凡例
- ● : 全員参加・出席
- ○ : 一部参加・出席
※更新が少し遅れる場合があります。最新のスケジュールはお近くの祭典親睦委員(T-Backs)メンバへお問い合わせください。T-Backsメンバは専用サイト内のイベントカレンダーで確認ください。
過去資料
- 2024年
- 令和6年度 見付天神裸祭
- 2023年
- 令和5年度 見付天神裸祭
見付天神裸祭とは
裸祭紹介動画 NEW
国指定重要無形文化財 見付天神裸祭 [制作:見付天神裸祭保存会]
国指定重要無形文化財 見付天神裸祭【神社・先供】 [制作:見付天神裸祭保存会]
国指定重要無形文化財 見付天神裸祭【觸番】 [制作:見付天神裸祭保存会]
国指定重要無形文化財 見付天神裸祭【輿番・権現(東区)】 [制作:見付天神裸祭保存会]
国指定重要無形文化財 見付天神裸祭【輿番・地脇(東中区)】 [制作:見付天神裸祭保存会]
役割紹介
- 先供
- 「先供の役割」(見付天神裸祭ガイドブック 平成20年度版より)
- 輿番
- 「輿番の役割」(見付天神裸祭ガイドブック 平成21年度版、見付天神裸祭ガイドブック 平成22年度版より)
- 一番觸
- 「一番觸の役割」(見付天神裸祭ガイドブック 平成23年度版、見付天神裸祭ガイドブック 平成24年度版より)
- 二番觸
- 「二番觸の役割」(見付天神裸祭ガイドブック 平成25年度版、見付天神裸祭ガイドブック 平成26年度版より)
- 三番觸
- 「三番觸の役割」(見付天神裸祭ガイドブック 平成27年度版、見付天神裸祭ガイドブック 平成28年度版より)
- 〆切
- 「〆切の役割」(見付天神裸祭ガイドブック 平成29年度版、見付天神裸祭ガイドブック 平成30年度版より)
もっと知りたい方へ
| 裸祭の歴史年表 | 見付天神裸祭ガイドブック 平成22年版より引用しています。 |
| 用語解説と注意事項 | |
| 裸祭の日程 | 見付天神裸祭ガイドブック 平成24年版より引用しています。 |
参加者の心得
伝統としきたりを引継ぎ、楽しくかつ安全なお祭りとするため、参加される方は下記の心得を必ず守ってください。
御斯葉おろし
- 22:00に矢奈比賣神社を出発します。深夜帯ですので小中学生は必ず保護者の同意を得るか、保護者同伴で参加してください。
- 服装は白いシャツに白い短パンです。
- 走るときに「オシ、オシ」と掛け声をかけます。
- 徒競走ではありません。神職・先供の前へ出ないように。
浜垢離
- 参加者は祭組で用意したバスを利用します。神社関係者・保存会以外の駐車場はありません。
-
浜辺の潔斎の時は以下を守ります。
- 安全第一を心がけます。
- 町内の役員や保存会の役員、ライフセーバーの指示に従います。
- 「浜の清祓」が済むまで後方で待ちます。
- 祭組ごとに潔斎します。
- 禊の服装は、大人連は町印の手拭い、晒のふんどしとします。子供連も大人連に準じますが、水着着用も可とします。
御大祭
- 梯団長や警固長の指示に従います。
- 各家庭では、軒提灯を掲げます。
- 道中練りに加わるときは、必ず練りの集団の後ろから入ります。
- 練りの中には各祭組提灯以外は持ち込みません。
- 觸番以外の人は絶対觸鈴には触りません。
- 中学生や高校生は、各祭組に用意している手首に白いテープを巻いて参加します。(白いテープを巻いている人の安全を皆で守ります。)
- 拝殿内の仕切り棒には乗りません。
- 鬼踊りで休憩後に再び拝殿に入るときは、正面のスロープから入ります。
- 堂入りの時以外、鬼踊りするときは白丁を脱ぎます。
- 神輿が出るときは、拝殿内の練りは二つに分かれ、拍手をして神輿を送ります。
- 神輿に絶対に触りません。
- 神輿が出た後は、拝殿から出て淡海国玉神社(総社)に向かいます。
- お供をする裸の練りが神輿に近づきすぎないように警備する役割を持つ〆切(富士見町)の人たちの指示に従います。
- 神輿が着いた総社の拝殿には輿番以外は入りません。
- 渡御が終わったら、総社の拝殿に参拝して「腰蓑納め」をしてから各祭組へ帰ります。
令和6年度からのルール NEW
拝殿周辺での見学時の注意事項
-
堂入りおよび鬼踊りは拝殿正面スロープ並びに濡れ縁に上がって見学することはできません。
一般の観客は拝殿東側からのみ見学することができます。 -
拝殿西側は裸衆の休憩エリアとなります。
このエリアに立ち入ることができる人は、裸衆および裸衆のサポートを行う関係者のみとなります。
関係者エリアに立ち入るためには、各町の手拭いと法被を着用し、かつ保存会が作成したリストバンドを着用することが条件となります。
※あくまでサポートを行う方に限ります。見学のみの方に対してはリストバンドの配布はしません。 -
拝殿周辺の混雑状況によっては、手水舎あるいは六ツ石で一般の観客は進入禁止となる可能性があります。
不用なトラブルを避けるためにも、各町関係者は「手拭い」「法被」「リストバンド」の3点の着用をお願いします。
エリア分け、および関係者エリアへの立ち入り方法については、矢奈比売神社境内図を参照してください。
過去資料
祭組体制の推移 NEW
- 令和7年
- 2025年9月21日~28日 NEW
- 令和6年
- 2024年9月1日~8日
- 令和5年
- 2023年9月17日~24日
- 令和4年
- 2022年8月28日~9月5日
- 令和2年
- 2020年9月20日~26日
- 令和1年
- 2019年9月1日~8日
- 平成30年
- 2018年9月9日~16日
- 平成29年
- 2017年9月17日~24日
- 平成28年
- 2016年9月4日~11日
- 平成27年
- 2015年9月13日~20日
- 平成26年
- 2014年8月24日~31日
- 平成25年
- 2013年9月8日~15日
- 平成24年
- 2012年9月16日~23日
- 平成23年
- 2011年8月28日~9月4日
- 平成22年
- 2010年9月5日~12日
- 平成21年
- 2009年9月20日~27日
- 平成20年
- 2008年8月31日~9月7日
- 平成19年
- 2007年9月9日~16日